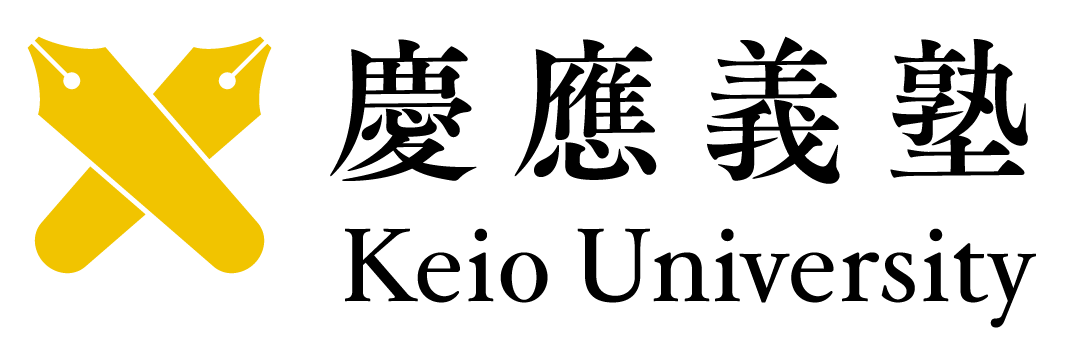研究
教員の研究紹介
教員からの研究レポート

認知発達研究室:発達をささえる脳とこころの研究
社会学研究科 心理学専攻
北 洋輔 准教授
私たちの研究室は、子どもたちの脳と心の発達を明らかにし、発達障害や学習のつまづきに対する適切な理解と支援を提供することを目指しています。
研究室では、この目標に向かって大きく2つのアプローチをとっています。一つは、基礎研究です。子どもの視覚・聴覚・社会性・運動機能など、さまざまな心的機能を対象に、心理学実験を行っています。実験を通して、それらの機能や背景にある脳機能を分析し、発達上のつまづきが生じる原因を科学的に解明しています。こうした基礎知見は、子どもやそのご家族にとって直接的なメリットは少ないです。しかし、データに基づいた知見を提供することで、"努力不足""ふざけているだけ"といった子どもたちのつまづきに対する誤解や偏見を取り除き、社会全体の適切な理解につながると考えています。
もう一つは、臨床活動です。発達上のつまづきのある子どもたちに対するアセスメントと支援を行っています。実際に子どもたちに接して、知能検査や認知機能検査を行い、それぞれの子どもの特性を把握します。そして、一人ひとりの特性に合わせた支援方法を提供したり、新たな支援技術を開発しています。活動は、学内では社会学研究科実習室を中心に行い、学外では、医療機関に加え、園や学校、教育委員会など行政とも協働して行っています。
これらの研究や活動は決して教員一人ではなし得ないものです。そのため、私たちの研究室は学生や院生が主役であり、これからも皆さんと一緒に取り組み続けいたいと考えています。

感情をめぐる心と脳、身体の関係性
社会学研究科 心理学専攻
寺澤 悠理 准教授
私たちは、目の前にある状況や、将来の予測、あるいは過去の回想、そして現実感のない空想に対してさえも心を揺さぶられ、その感覚を感情として理解しています。それでは、感情はどのようにして心に浮かび上がってくるのでしょうか。そして、その個人差はどこから生まれるのでしょうか。私たちの研究室では、この疑問を心と脳、そして身体の働きの関係性から理解しようと試みています。強い感情を感じた時に同時に起こる心臓や呼吸などの活動の変化は、心の働きの結果として現れるだけでなく、これらの変化を感じること自体が、感情そのものの内容や鮮明さに影響を及ぼしている、という仮定のもと、心理学や心の動きに伴う脳活動を観察する認知神経科学の手法を用いて研究をしています。
具体的には、不安などの感情を感じやすい人や反対に自分の感情を感じづらい人は、感情に伴う身体反応の感じ方に特徴があるのか、またその特徴に関連する脳活動があるのか、といったことを調べています。このために、複数の自律神経活動を同時に計測する機械や、脳活動を観察するための機械などを使用することもあります。また、個人の感情の感じ方の特徴を質問紙や面接を用いて調べ、身体や脳活動との関係性を見出そうと試みています。最近では、身体反応の感じ方を変化させるトレーニングや、前述の脳活動の変化によって感情の感じ方や気分状態に変化が生じるのか、といった視点からの研究も行っています。
心と身体のつながりを科学的な手法を用いて紐解き、その関係性についての理解を少しずつでも進めたいと考えています。

祈りの場から再考する東アジアの社会と文化
社会学研究科 社会学専攻
藤野 陽平 教授
台湾を中心としながら東アジア各地で人類学調査を続けてきました。台湾は東アジアにおける民主主義の代表の地位を確立していますが、それは新しいものではなく、戦後、ながらく独裁政権下で市民の自由は制限されてきました。
歴史を振り返ると原住民と呼ばれる先住民族が暮らしていた台湾に徐々に漢民族が移住し、その後も大航海時代にはオランダとスペインが、アヘン戦争の後にはイギリス、日清戦争の後に日本、戦後は中華民国といったように、新しい支配者が次々とやってきました。そのため、複数の植民経験がミルフィーユのように重なりあって、いろいろな出自の人々が持ち込んださまざまな文化が台湾を多様性のある色鮮やかな社会にする一方で、その度ごとに熾烈な勢力争いもありました。
帝国日本による植民地統治、戦後の228事件や国家暴力、1970年代からの民主化運動を経て、2014年のひまわり学生運動と歴史的な大きな出来事も起き、これらは歴史学や政治学、国際関係学のジャンルで積極的に研究されてきました。
そして、そこには必ず人々の祈りがありましたが、これまであまり注目されてきませんでした。私はこうした祈りの場に身をおきながら、人類学的に捉えなおしています。人類学はエスノグラフィという長期間現地で暮らし、そこで出会った人々と一緒に考えてみるという方法を用います。祈る人々の息づかいを感じながら同じ場所に寄り添うことで見える世界からこれまでとは違った東アジアの姿を描いていきます。

教育概念の哲学的分析
社会学研究科 教育学専攻
渡邊 福太郎 准教授
概念は手に取ることも見ることも、実験室に持ち込むことも計測することもできません。それにもかかわらず、私たちの知覚や思考は概念によって規定されており、さらには新たな概念の誕生によって、私たちの経験の様態は大きく変貌します。哲学的な営みの特徴は、こうした概念それ自体を考察対象とする点にあると言えるでしょう。
教育という概念を考察対象にする場合、ある特有の困難が生じます。私たちは自らの経験から、何を「教育」と呼び、何をそう呼ばないかを区別しています。「教育問題」をめぐる対立が、しばしば人格間での衝突の様相を呈してしまうのも、個人によって自明視される教育観の背後に、その人自身の人格形成プロセスが控えているからにほかなりません。このとき、教育概念にあえて限定的な定義を加え、誰もが合意できる理論を構築することによって、衝突を一時的に回避することもできるでしょう。そのかわり、私たちひとりひとりの具体的な人格形成のプロセスは捨象されます。これとは逆に、教育概念を拡張する方向へ進むこともできるでしょう。個々人の人生は、それぞれが教育概念の一側面を照らし出し、ときには概念それ自体に変容をもたらすものとして位置づけられます。
現在の私は後者の方向性を取っています。教育概念の豊かな含意を明らかにするとともに、新たな方向への拡張可能性を探り続けることが、教育哲学という学問分野に特徴的な営みであると考えています。
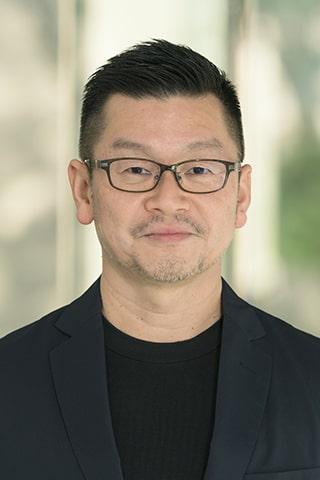
一人ひとりの人間の「生」へのダイナミックな接近
社会学研究科 社会学専攻
小倉 康嗣 教授
人びとのライフストーリーを社会学的な見地から調査研究しています。ライフストーリーとは個人の生(life)についての口述の物語です。つまり人びとの生の語りをインタビューすることがライフストーリー研究の重要な営為になるわけですが、ライフストーリー・インタビューは単なるインタビューではありません。そこには独自の問題意識と視点があります。
第一に、個人の生の全体性への接近です。語り手の属性(社会的カテゴリー)や語りの内容(事実情報)だけでなく、それらを背負って語りが生成されていく人生過程上の経験とそれが生かされている関係性の堆積こそを見ていこうとします。そのようなインタビューのなかで第二に、「いま・ここ」と「あのとき・あそこ」のダイナミズムによるストーリー生成がなされます。それは語り手の生の全体性が凝縮され、語り手を突き動かすものとして「いま・ここ」のインタビューの場で「あのとき・あそこ」のことがパフォーマティブに語られる(あるいは沈黙される)ストーリーです。これらは第三に、語り手と聞き手の対話的相互行為のなかで引き起こされ、その後の考察も含めたプロセスのなかで、語り手(調査協力者)の生にも聞き手(調査研究者)の生にも異化をもたらします。
つまり、このような生の全体性に根差した対話的インタビューとその考察のなかで、調査協力者だけではなく調査研究者自身の枠組みも(さらには生も)同時に問われていくわけです。そしてそのプロセスそれ自体が、豊かな社会学的示唆を与えてくれる探究の対象となる。そのような意味でライフストーリー研究は、ダイナミックで生成的な研究です。
いま私は、原爆体験の継承の現場でこのライフストーリー研究のアプローチを試みています。そこでは、原爆体験の風化(形骸化・他人事化)を超えていく経験的地平が、まさしくダイナミックに生成されています。

学校教育現場はいかなる「実践知」を積み重ねてきた(いる)のか
社会学研究科 教育学専攻
藤本 和久 教授
カリキュラム研究の一分野に「カリキュラム開発史」研究があります。プロジェクト・メソッドはいかにうまれたのか、デューイ実験学校はパーカー・スクールとどのような共通点を有していたのか、などについて、主たる論者の文献をひもときながら解明していく面白さがあります。ですが、教育史のテキストに描き出されるような、そのような典型的なカリキュラム理論や教授理論が、実際の学校現場ではどのように受けとめられ、実践され、時には改良が加えられ独自の発展をみたり、時には実践不可能とみなされ放棄されたりしていたのでしょうか?
私の専門分野である教育方法学では、実践と理論の「緊張関係」がしばしば指摘されます。現代日本の学校教育現場は、行政が示した教育課程もこの問題に絡まり合って、この問題をより複雑化させています。学校教育現場における実践の変遷史は、教育学の理論史とシンクロしてきたわけではありません。「実践知」の蓄積それ自体が新たな問いを呼び込み、さまざまな挑戦を促してきました。実践と理論の関係を学校教育において考究していくということは、まさにこのような双方の歴史性へのまなざしを抜きには進めえません。
学校教育現場への豊かな関与をもちながら、そこに「実践知」の歴史的奥行きを見出し、今の(今日の、本時の)実践の意味を問うていく姿勢を大切にしたいと日々考えています。

過去と現在の往還から教育への問いをひらく
社会学研究科 教育学専攻
綾井 桜子 教授
私の専門分野は、教育思想史と呼ばれる分野です。教育思想史をどのように捉えるのかについては諸説ありますが、教育という概念や営みを歴史の文脈に位置づけることによって、教育の自明性を問い、日常のなかで見失われつつある教育の考え方や意味を再発見することに向けられた領域であると言えます。
私たちにとって身近な学校教育は、近代という時代の産物でありますが、近代的な教育の成り立ちやそれが抱えた課題は一様ではありません。私自身は、フランス近代を対象として、知識と人間形成をめぐる考え方はどのように変容し今日に至っているのかについて、大学への進学準備教育と教養形成をともに担っていた「リセ」に着目しながら研究しています。あわせて、生の全体を視野に収めた人間形成を志向する教育の歴史とはどのようなものであったのか、また、教育を学問として問うとはどのような知的営為を意味するのかを、今日の教育学研究の動向に照らして探究することにも関心があります。
現在のグローバル化のなかで教育には急速な変化が求められ、一定の資質や能力を育成することに関心が向けられる一方で、教育への問いは、ある意味、一様になりつつあります。近代教育を成り立たせた歴史を辿ると同時に、近代的な視点では見出しえなかった教育の諸相を発見し、教育の意味を根本から問い直すところに教育思想史のアクチュアリティーがあると言えるのではないでしょうか。

フィールドワークをとおして生活の変化を捉える
社会学研究科 社会学専攻
佐川 徹 准教授
私の専門は文化人類学とアフリカ地域研究です。「21世紀はアフリカの時代」といわれることがあります。実際、今世紀に入ってから、アフリカの多くの国では経済成長が進み、若者が多数を占める社会は活気に満ちています。その一方で、急激な社会の変容は人びとのくらしにひずみももたらしています。私は、人びとが生活を営む現場に身を置いて調査を進めるフィールドワークをとおして、躍動するアフリカの姿を捉えようとしてきました。
最近、私が関心を抱いているテーマは食生活とその変化です。アフリカの食といえば、食料不足や飢饉などの「問題」ばかりが注目されがちですが、アフリカにも多様で豊かな食と料理の伝統があります。現在、その伝統は大きく揺らいでいます。グローバル化が進むなかで、新たな輸入食材や多くの加工食品がアフリカの農村部にまで浸透しつつあるからです。
もっとも、アフリカの食が画一化されつつあるという理解は一面的です。私が調査をしているガーナ共和国の村落にくらす人たちは、日本でくらす私たち以上に、食の安全性や食が健康にもたらす影響に関心を寄せています。そして、地元で採れた食材を「ナチュラルな」ものとして評価したり、これまでの調理法を見直したりしながら、毎日の食事のあり方を再構成しているのです。人びととおいしい料理を食べながら会話をすることで、くらしの細かな変化を明らかにしていけるところに、人類学的なフィールドワークの醍醐味があるといえるでしょう。

社会における「責任」と科学
社会学研究科 社会学専攻
常松 淳 教授
社会における「責任」のあり方について社会学的な観点から研究しています。社会で特異な役割を果たすのが法的責任です。例えば民事責任(損害賠償責任)の場合であれば,当事者同士が様々な損害について責任の有無や程度について裁判所で争います。法的責任の決定は法専門家に固有の思考法によって先導されますが,それは必ずしも当事者本人の期待に沿ったものになるとは限りません。これまでの研究では,両者の対立を読み解くことを通じて,日本社会において(法的)責任が担っている意味の一端を解明しようとしてきました。
さて,民事であれ刑事であれ,法的責任を問う場面では人々の行為が問題とされます。一方で,人間の行動・行為は経験科学(自然科学・社会科学)の対象でもあり,近年では神経科学やデータサイエンスの発展とも相俟って熱心に研究されています。そしてこの科学的な知見に基づいた人間観もまた,法や社会制度,日常道徳が想定している人間像と相容れない部分を含んでいます。実際,一部の論者は,現在の司法制度,特に刑事司法が"科学的に誤った"人間観に基づいており,即刻根本的に変更されるべきだと主張しています。ここでも,両者の齟齬を解剖することで「責任」のあり方を探ることが可能になります。またこのとき,果たして科学的「証拠」とは何であり,その証拠から何が導けるのかも大きな問題です。現在はこれらのテーマを中心に研究を進めています。
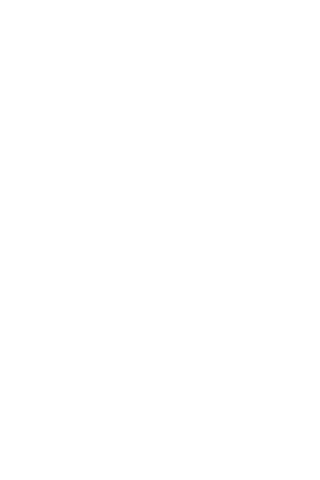
一人ひとりの子どもの育ちを理解する
社会学研究科 教育学専攻
藤澤 啓子 教授
立つことができてから歩くことができるといった、一般的な発達の姿はありますが、個々の子どもの成長のありようは子どもごとに違っており、からだと心の育ちのどこを見ても個人差があるものです。発達心理学と行動遺伝学の理論を基盤に人間の発達における個人差について研究する発達行動遺伝学は、生物学的要因やさまざまな環境要因が複雑に影響し合いながら、子ども個々に異なる「その子らしさ」が現れるプロセスを明らかにしてきました。
保育園や幼稚園で子ども達が遊ぶ様子を丁寧に観察していくと、子ども達は子ども達なりに社会関係を築き、さまざまな社会的なやり取りをおこなうことや、また第三者の立場からやり取りを見ているなど、同じ教室で同じ時間を過ごしていても、子ども達それぞれが経験していることは必ずしも同じとは言えないということがわかります。こうした日常的な経験の一つひとつも、「その子らしさ」につながっていくと考えられます。
子ども達一人ひとりが、かけがえのない子ども時代を子どもらしく、毎日楽しく、健やかに過ごして成長していくために、大人は何ができるでしょうか。子ども個々に異なる発達の姿を理解したうえで、どのような家庭内・家庭外における教育環境を作っていけば良いのか、そのためにはどのような課題があるのか、探求すべきクエスチョンにあふれています。

ニュースの分析を通じて「社会」のあり方を研究する
社会学研究科 社会学専攻
山腰 修三 教授
私の専門は、メディア研究、ジャーナリズム研究、マス・コミュニケーション研究と呼ばれる領域です。とくにその中でもニュースを主な分析対象としてきました。ニュースを社会学的に研究する意義はどこにあるのでしょうか。それは、私たちが日常生活の中でニュースを通じて「社会」を確認している点にあります。現代社会で生じるさまざまな出来事――例えば戦争やパンデミック、あるいは政府の政策決定――は私たちの公的・私的な生活に影響を及ぼしますが、多くの場合、私たちはそれを直接経験することはできません。新聞やテレビ、あるいはソーシャルメディアのニュースを介して社会的な「現実」が共有され、それを通じて現代の政治社会は成り立っているのです。
しかしニュースは無色透明なものでも、出来事を鏡のように正確に映し出すものでもありません。ニュースはいわば、社会の利害関心や価値観を反映し、出来事を特定の視点から意味づけるものなのです。そこからニュースがどのように制作されているのか、そして「社会的現実」をどのように表象し、あるいは構築しているのか、という問いが導かれることになります。いわば、社会的な現実の意味づけを可能/不可能にする力学をニュースの分析から読み解くことが、ニュース研究の主要な目的なのです。
さらに近年は、ニュースの生産や流通がソーシャルメディアやプラットフォームの登場などによって根本から変化し、ニュースを研究することがますます複雑になっています。それは、これまでのようにただニュースの内容を分析するだけではこの領域の研究が成立しなくなっていることを意味します。そのためには新たな理論や分析概念が必要になります。このように、日々開拓すべき領域が拡大していることも、ニュース研究の魅力だと言えます。

「シンボル化の政治学」を構想
社会学研究科 社会学専攻
烏谷 昌幸 教授
わたしの専門分野は、政治コミュニケーション研究と呼ばれる分野です。二度の世界大戦を経験した20世紀に米国で誕生した学問分野で、当初は戦時プロパガンダ、政治指導者の演説レトリック、選挙キャンペーンの効果などの研究を中心に発展を遂げました。
この研究分野は、20世紀から21世紀へと世紀を跨いで転換する中で、主に3つの点で重要な変化を被ってきたといえます。第一に、インターネットに代表されるメディア技術環境の変化。第二に、言語論的転回と一般に総称される人文・社会諸科学を広く席巻した知的変革。第三に、アメリカにおけるトランプ現象、中国の覇権国家としての台頭、ロシアによるディスインフォメーションの影響拡大など既存の自由民主主義の価値前提を動揺させる現実政治の動き。
これらのインパクトを踏まえながら、政治コミュニケーション研究の枠組みをどう根本的に再構築していくことができるかが現在問われています。わたし自身は政治シンボル論を批判的に再構成し、シンボル化の政治学として再構成することで現代のメディア社会に相応しい政治コミュニケーション研究をつくることができるのではないかと考えています。
政治シンボルの研究を、国旗や政治スローガンなどの狭いテーマに限るのではなく、人間が生物として有する根源的な「シンボル化の欲求」に着眼して、人間社会の中でどのような条件のもとで「強いシンボル」(カリスマ的指導者、衝撃写真・映像、人々の強い感情、欲望を凝縮した言語シンボルなど)が生産され、それがどのように政治的、社会的に利用されていくのか、そのプロセスを詳細に探究する学問をつくりあげたいと考えています。

マージナルな教育について歴史的に研究する
社会学研究科 教育学専攻
山梨 あや 教授
私の専門分野は日本の近現代教育史です。教育史というと「学校」や教育制度の歴史と思われることが多いのですが、私の研究関心はどちらかといえば、「学校」や教育制度の境界線、マージナルなところに見いだされる「教育」とその意味を歴史的に明らかにすることにあります。大学院生時代から、趣味や私的な営みとして捉えられがちな読書という営みがどのように「教育」の対象としてクローズアップされたのか、具体的にどのような教育活動が展開されたのかを図書館を対象に、1900年代から1960年代の比較的長期に亘るスパンで検討してきました。どちらかと言えば、読書という知的営みからは周辺化されている人々に焦点を当てたのですが、研究の過程で近現代日本の知的営為には「学校教育」という枠組み以外でも性差、地域差、階層差が存在していることをまざまざと実感しました。と同時に、学校教育とは異なる回路で「知」が人々の間に普及していったのではないか、とも考えるようになりました。
研究生活の入り口では学校外の教育にばかり注目していましたが、アマノジャクな性格も手伝って、最近は学校と学校の外―家庭や地域―がどのように関係して「教育」という営みを成立させているのか、という問題に関心を持っています。長野県の小学校に保存されている1930年代から60年代に至るまでの学校資料を読み解く中で、学校は家庭や地域を一方的に「啓蒙」したり教育したりするだけではなく、家庭や地域との相克を含む一種の緊張関係の中で教育を模索していたことが明らかになってきました。戦後初期は、学校が子どもだけではなく戦前の教育を受けた親世代に「民主的」な考え方を理解させることに心を砕いており、この時代に着目して「民主主義」や「民主的なるもの」が親世代にどのように教育されたのかを明らかにすることも目下の研究課題の一つです。
1960年代後半になると、学校、教師、さらには学校教育制度そのものに対する疑念の兆しも見られるようになり、学校と家庭、地域の関係はより複雑化していくことになります。このような複雑化した関係性を前提として、「教育」というものがどのように考えられていたのかを学校側の視点からだけではなく、家庭の視点から明らかにしていくことにも関心があります。
大学院に入った時は、自分が小学校の資料を読んだり、1960年代の地域教育雑誌などに関心を持つようになるとは全く想像しませんでした。自分の生まれた年に近い資料を読む一方で、学校が学校外の組織―家庭や地域―にまなざしを向け始める時期、つまり明治期の学校資料や教育雑誌なども読んでいます。研究とは必ずしも一直線に進むものでも進めるものでもなく、様々に張り巡らせた糸を撚ったり、時には解きほぐして編み込んだりしていくものなのかもしれません。このような研究を可能にするのは、資料や文献を探して読み込むことは勿論、研究について教員、先輩、同輩、後輩と忌憚なく意見を交換することです。新しく入学される皆さんと共に、豊かな研究が出来る場を作っていきたいと思います。

メディアの社会心理学から人間と社会を探求する
社会学研究科 社会学専攻
李 津娥 教授
私たちは、メディアのオーディエンスとして様々なメディアコンテンツを消費しています。消費者、生活者、有権者としての価値判断や意思決定において、また、自己、他者、社会に対する認識において、私たちはメディアをどのように利用し、どのような影響を受けているか。こうした問題にメディア心理学の視点から研究しています。大学院の博士課程では、広告のエンターテインメント性に注目し、広告に対するユーモア知覚が広告効果過程に及ぼす影響について研究をしていました。今は、引き続き、多様化するメディアや企業環境を踏まえ、人・コト・モノをつなぐ広告や関連するメディアコンテンツがどのように発信、共有され、消費者としての私たちの心と行動にどのような影響を及ぼしているかについて研究を行っています。広告は社会問題や政治に関する情報を伝え、説得を行うコミュニケーションでもあります。政治広告や政治キャンペーンが有権者の意識や行動に及ぼす影響も私の重要な研究テーマです。政治コミュニケーションに関しては、女性政治家とメディア、政治志向による政治情報の消費と共有などの研究にも取り組んできました。メディア・コンテンツは、国内のみならず、国や文化を超え消費されています。トランスナショナルな空間に生きるディアスポラが、文化的アイデンティティを維持し再構築する上で、母国メディアの利用がどのような意味を持つかについても研究を行なっています。

つながる歴史へ
社会学研究科 社会学専攻
太田 淳 教授
私は18-20世紀インドネシアを中心に様々な角度からの歴史研究を試みていますが、一貫して「つながる歴史」を描こうとしてきました。「つながる」というのは、それまで一つの社会や一つのシステムと見なされていたものの内部要素が、様々な経路を通じて結びつくダイナミクスと捉えられます。私たちは習慣的に一定の社会やシステムといった枠組で世界を観察する傾向がありますが、人間や人間社会はそれらを超えてつながる力を持つことを見出したいのです。博士論文から取り組んだ西ジャワのバンテンという地域の研究では、オランダ東インド会社による支配が進行する中で、地域社会の有力者が商品作物(主に胡椒)の栽培を強制する会社の制度を利用して自らの影響力を強めたこと、胡椒生産者は作物を地域有力者でなく外部の民間商人に売却して海外市場とつながったことなどを論じました。そうした民間商人の多くはマレー海域の海洋移民で、資料ではしばしば「密輸商人」や「海賊」と記されますが、彼らは異なる地域の需要と供給を結びつけました。この需要は、18世紀中国の経済発展地域で台頭した中間層の間で、胡椒やナマコや燕の巣などの外食や顕示的消費が増えたことから生まれ、東南アジアの生産地と中国経済がつながりました。私は海賊だけでなく社会の中心にいない人々が異なる経済や文化をつなげる働きに関心があり、女性や混血者の役割にも注目しています。最近では、様々な気候変動が人間の生業や社会構築に与えた影響に着目し、歴史気象学という自然科学的知見と社会経済史をつなげることにも取り組んでいます。

進化から人間の行動と心理を探る
社会学研究科 社会学専攻
平石 界 教授
私の研究の中心には、「心」は自然淘汰による進化の産物であるという考えがあります。心理学を学んだことのある方は、人間の心にはさまざまなバイアスがあることをご存知だと思います。バイアスのために人間はしばしば非合理的なことを行います。お金を払ってしまったからというだけの理由で面白くもないビデオを見続けたり(サンクコストの誤り)、あるグループに所属しているというだけで相手を見くびったり(偏見)。こうしたバイアスはなぜ存在しているのでしょうか。人間が進化する過程においては、一見すると非合理的なバイアスにも、良い面があったのかも知れません。私たちの「心の仕組み」に進化的な意味があるのか考えるのが進化心理学です。私はこれまで進化心理学の視点から、内集団びいき・外集団排除がもたらす思考バイアス、他者への信頼とパーソナリティの個人差の進化、指の長さの比を用いての胎内環境と性的指向の関係の検討、公共財ゲームにおける個人差への遺伝と環境の影響といったテーマを扱ってきました。現在は、SNSでの炎上に見られるような、他者への道徳的非難の進化を中心に、道徳性の進化にかんする研究を進めています。加えて近年は、心理学における再現性危機に関連して、進化心理学の古典的知見の追試にも取り組んでいます。

知識と社会学の歴史性と社会性
社会学研究科 社会学専攻
森川 剛光 教授
私の主な研究業績には、マックス・ヴェーバーを中心にした草創期の社会学とその科学論的・方法論的基礎づけに関する、いわゆる社会学史に属する研究と、ニクラス・ルーマンの理論を応用した、マクロ歴史社会学と世界社会論に分類される研究があります。前者では19世紀ドイツ語圏において社会学が経済学から分出してくる過程で、ヴェーバーと同時代人の経済哲学者フリードリヒ・ゴットルにおいて、社会学の基礎概念である「行為」、「意味」、「日常」などが、いかに発見され、問題化され、基礎づけられたのかについて、博士論文で議論しました。引き続き19世紀末~20世紀初頭ドイツ語圏での、周辺諸科学(経済学、哲学、人類学等)と社会学との関係を追求しています。後者では「ゼマンティク」と呼ばれる社会的に共有される知識(観念・通念)の変化と社会構造の変動、コミュニケーションメディアの発達の相関関係を、特に「愛」の観念について、日本における江戸時代から大正時代までの歴史的変動と現代の世界社会における地域的差異を中心にして研究しました。最近の研究関心は紛争後社会における「赦し」と「融和」の問題に加え、マルティン・ハイデガーとハナ・アーレントの哲学的人間学を参照しながら、社会学的行為論の再検討をおこなっています。これまでの行為論は行為を「制作」をモデルに考えすぎていました。この制作=行為モデルは、様々な挑戦を受けてきましたが、それを背後で支えている、存在論や時間論まで立ち入って検討されたことはありませんでした。

「美」の探求から人間性の本質を理解する
社会学研究科 心理学専攻
川畑 秀明 教授
私の関心の中心は、人の認知や思考における主観性や価値体験に関する心や脳の働きについて理解することを通して、人間性の根源や本質を多面的に明らかにすることにあります。大学院の博士課程までは、赤ちゃんの視覚、特に視覚的補完という遮蔽された物体の背後にあるモノを知覚できる過程の発達や、成人の視覚情報処理過程について研究をしていました。学位を取得後ロンドン大学に留学し、脳の働きを捉える計測技法を学ぶとともに芸術感性や美の背後にある脳の仕組みを理解する神経美学という研究を始めました。私たちの研究では、美を報酬系という脳のネットワークやドパミンなどの神経伝達物質の働きとして捉えています。現在は、芸術美だけでなく、対人魅力の研究も精力的に行い、抗加齢 医学や美容科学との連携も図っています。今後は、様々な神経伝達物質が関与する多様な脳の仕組みやホルモンの働き、免疫系と美の感じ方や美の現れ方との関連も明らかにしたいと考えています。美しさ、魅力、愛情などの人間性の基盤の理解は、これまで文学や哲学のテーマと考えられてきており、その科学的解明は始まったばかりです。日常的なトピックスを問題設定しやすいので取っ付きやすい反面、哲学や美学、芸術史など人文学における諸問題への深い理解と進化や分子生物学、工学などの自然科学からの説明や理論化が必要とされる難しさもあります。美の解明は、国内外の色々な分野の研究者や企業との協働が不可欠な究極的な学際研究であり、常にワクワクドキドキが伴う楽しい探求です。

社会階層と不平等:マクロな制度編成と国際比較
社会学研究科 社会学専攻
竹ノ下 弘久 教授
社会学の立場から、社会階層と不平等と呼ばれる研究領域を中心に、調査研究を行ってきました。その中でも、社会において不平等の生成、維持に関わるマクロ、メゾ・レベルの諸制度が果たす役割に注目してきました。考察の中心は、日本社会にありますが、日本社会の制度の果たす役割を可視化するために、他国との比較を重視して研究してきました。私自身のこれまでの研究では、東アジア諸国における不平等の国際比較を通じて、教育と労働市場をめぐる諸制度の相違が、不平等のあり方にどのような違いをもたらすのか検討してきました。こうした階層研究を進めるにあたり、日本社会全体の不平等構造と制度の関わりを明らかにするだけでなく、グローバル化という社会変動が不平等構造にどのような変化をもたらすのかを考察する観点から、海外から日本に移住してきた国際移民に注目し、かれらをとりまく制度と不平等との関係を考察しています。日本社会を中心とする階層研究を、国際的な視野から進めていくために、アジアや欧米諸国の研究者との研究交流と、国際的な共同研究にも従事しています。

モノの次元に隠された「人間くささ」を発見する都市の技術社会史をめざして
社会学研究科 社会学専攻
近森 高明 教授
私の学問上のモデルは、W.ベンヤミンとW.シヴェルブシュ、G.ジンメルで、彼らの仕事を範例としつつ、おもに近現代日本の都市環境の変容を、文化社会学、都市空間論、そして技術社会史が重なり合う視座から探究しています。とくにシヴェルブシュの、ごく些末な技術史的事象を扱っているようでいて、そこからより一般的な知覚や想像力のパラダイム転換を導きだす手際に憧れ、さまざまな主題のもとに研究をすすめてきました。たとえばインフラ的技術。街灯、電柱、送電鉄塔、エアコンなど、自明すぎて問いの対象にならないような技術的事象にあえて注目し、その歴史的変遷を紐解いてみると、私たちの生活環境がどのような偶発的条件の積み重ねで成立しているのかがみえてきます。あるいは地下空間の利用。1920年代の地下鉄の導入や高度経済成長期の地下街の急激な増殖など、地下利用の変遷を眺めてみると、人びとを一種のフローとして扱う技術が、いかに都市に埋め込まれてきたかが顕わになります。都市空間にまつわるさまざまな事象を、端的なモノの次元に還元すればするほど、むしろ人間くささが浮かびあがってくる、そのような瞬間をとらえる社会学的な文体を模索したいと思っています。

赤ちゃんの脳に社会的人間の起源を探る
社会学研究科 心理学専攻
皆川 泰代 教授
私の研究の軸は言語、社会性を含めたコミュニケーション能力の発達にあり、乳幼児-思春期を対象とした研究を行ってきましたが、学生達とも絵本や玩具の研究、運動発達研究、成人の研究など色々な「スピンオフ」研究も行ってきました。それら異なる研究が色んな意味でつながることも多く、人間の不思議を見たようなワクワク感があります。例えば最近の不思議は言語野の1つである下前頭回(IFG)です。新生児に言語を聞かせるとIFGが活動することも多く、言語機能の原型が新生児にもあることを見出してきました。しかし、新生児のIFGは、基本的な脳機能回路を反映すると言われる安静時脳活動においても、脳回路全体のハブ的役割をし、特にIFGと側頭部の繋がりの重要性が見えてきたのです。なぜIFGなんだろう?と謎は深まるばかりです。そのような時に成人の2者間の社会的相互作用時の脳活動同時計測や乳幼児の運動研究などが様々なヒントを与えてくれました。言語、運動、社会性、知覚、様々なキーワードがIFGを通して繋がってきます。赤ちゃんの脳にはコミュニケーションをする社会的人間として進化してきた謎がまだまだ隠されていそうです。

精神医学の人類学:うつ病、認知症の台頭に見られる「ライフサイクルの医療化」
社会学研究科 社会学専攻
北中 淳子 教授
精神医学を中心とした、近代においてグローバルに展開された「医療化」の現象について医療人類学の視点から研究しています。特に、20世紀を通じてそれほど問題視されなかった「鬱」が、1990年代以降「うつ病」として病理化され、世界的に大規模な精神医学的介入の対象となった「医療化」現象について考えるために、臨床現場で長年フィールドワークを行ってきました。現在は、ストレスチェック等を通じて、仕事をめぐる日常的苦悩が精神障害として監視の対象となり、老いによる主に認知機能の衰えが「認知症」という病理として捉え直される、ライフサイクルの医療化について調査を行っています。同時に、心理検査や疫学を用いた医療的スクリーニングに基づく新たな管理システムや、都市像の構築の動きに関して、その前提となる人間観や世界観について、人類学的視点から考察しています。「病いの経験」に関して、当事者の視点に根差した科学知を産み出そうとする国際的な動きにも着目し、海外の人類学者・歴史家・医師との交流や共同研究を進めています。

「東アジア海域世界」と「良心的兵役拒否」
社会学研究科 社会学専攻
金 柄徹 教授
主な研究を二つご紹介します。まず、「東アジア海域世界」における倭寇・家船・海民の歴史と文化を歴史人類学の立場から研究しています。日本・中国・韓国を繋ぐ「東アジア海域世界」では、古来より多くの交流がなされてきたにもかかわらず、海に携わってきた人々の活動や文化は既存の陸地中心の視点からは十分に読み取れず、またこの海域は、断絶された境界(空間)としてすら認識されてきました。日中韓の陸地権力から周辺に位置づけられてきたこの海からの視点を確保することで、既存の陸地中心(自国中心)の歴史が相対化され、読み直される可能性が大いにあると感じています。もう一つ、「良心的兵役拒否」問題を研究しています。韓国では、男性は約2年間を軍隊で服務することとなっていますが、南北の分断が続く中、兵役は「聖なる義務」であるとの認識が強く、兵役問題に触れることは長らくタブー視されてきました。しかし、2000年代に入り、宗教・思想・信念に基づき、兵役を拒否する若者が増え、「良心的兵役拒否」問題は大きな社会的イシューとして議論されつつあります。今後、韓国社会がこの問題にどのように向き合っていくのかを見極めて行きたいと思っています。

優れた学校教員を育てる方法を多角的に探究する
社会学研究科 教育学専攻
佐久間 亜紀 教授
「いい先生」「力量の高い先生」とは、具体的には一体どのような教師のことをいうのでしょうか。私の専門は教育方法学で、学校教員の力量を高める方法や養成カリキュラムを、主に比較史的アプローチによって探究しています。時代や国や社会によって「優れた教師」の定義や要素は大きく変化しますし、教職に求められる専門性の内実も異なります。それゆえ私は、主に19世紀以降の日本とアメリカの教師教育の歴史を、教職の専門性の史的展開という観点から探究しています。私の研究の独自性は、この探究に女性史・ジェンダー史の視点を導入した点にあります。多くの国で教職は女性化されています。つまり、教育や教職をめぐる問題は、子どもを誰が育てるか、社会化された子育てが社会にどう位置づけられてきたのか、という問題と不可分なのです。新たな研究視角から、先行研究が見過ごしてきた事実を発見する作業は、スリリングな知的興奮に満ちています。さらにこれらの学術的知見をもとに、現代日本の教育現場における実践的問題の解決も探究しています。大学では教員養成の改善に取り組み、学校現場では授業研究や教員研修づくりに、現場の先生方と共働しながら取り組んでいます。

ゲーミング・シミュレーションを用いた環境問題の解決
社会学研究科 社会学専攻
杉浦 淳吉 教授
環境問題への対処行動に関するリスクコミュニケーションについて社会心理学の立場から研究しています。環境問題は、健康や経済の問題など多様なリスクとかかわっており、こうした問題の解決をゲーミング・シミュレーションという手法で検討しています。ここでゲームとは、現実問題の構造をルールや様々な変数からなる抽象的世界であり、目的に沿ってプレーヤの様々な行動が展開されます。ゲーム終了後にはプレーヤがゲームで起こった出来事を振り返り、その経験と現実世界との関連を考察します。ルールに応じたプレーヤの意識や行動の変化といったことが研究の対処となりますが、プレーヤ自身がゲームへの参加によって多くを学ぶことも非常に重要な目的です。環境配慮行動の大切さを伝える「説得納得ゲーム」や利害調整や合意形成を行う「ステークホルダーズ」といった教育・研究用のオリジナルゲームを開発しています。エンタテイメントが目的のボードゲームやカードゲームでも活用方法の工夫次第で他では得られない有益な学びにつながります。大学院の講義でもテキストを読むだけでなく、実際にゲームをプレイしたりデザインしたりすることで問題を多層的に捉えていきます。
研究力と実践力を鍛える社会学研究科実習室
社会学研究科
皆川 泰代(心理学専攻教授・社会学研究科実習室運営委員長)

社会学研究科実習室(以下、実習室)は、大学院生の実習施設として設立されました。当初は、三田キャンパス内、現在の南館のある場所の1階に建築された一軒家の建物。これは、臨床心理学研究において、来談者(クライエント)の方と大学生との動線が交差しないよう、プライバシーを確保するための配慮でした。
以来、大学院生の修士論文、博士論文の研究など、教育目的で活発に利用されてきました。設立時から、以下のような研究が、実習室を活用して行われています。社会学専攻が主導してきた、カウンセリング技法・心理アセスメント技法の習得、パーソナリティ研究、実験社会心理学研究。心理学専攻が主導してきた、行動修正実習授業、行動療法技法の習得、発達障害児支援の実践と研究、乳幼児の行動や脳機能の発達研究。教育学専攻が主導してきた、幼児や成人の知能検査実習、ふたご調査研究、幼児の集団活動研究。
その後、いくつかの移転を経て、2011年に現在の南別館3階に拠点を構えることになりました。現在の実習室は、集団で子どもたちが遊べる「プレイルーム」、個別発達支援に利用しやすい「訓練室」、青年や成人の方たちとの面談、聞き取り調査、基礎実験ができる「面談室1」、「面談室2」からなっています。この他に、近赤外分光法(NIRS)という脳機能計測を行う防音キャビンや研究データの保管のための保管室もあります。
プレイルームと訓練室は、ワンウェイミラーで仕切られていて、両室の様子をモニターするための「観察室」があり、相手から意識されずにデータの収集や母子並行面接などが可能になっています。プレイルームと訓練室を観察室からモニターし、映像をデジタル動画として記録することができます。
また、心理検査、発達検査、言語検査、認知機能検査、運動検査、適応行動検査、ストレス検査など、日本で用いられている検査の多くを所有しており、大学院生の教育と研究に供しています。
大学院生の実習時間を確保するため、実習は授業時間以外にも活発に行われています。例えば、2001年から開始された「臨床発達心理士」(一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構)の資格認定には、修士課程での関連分野の単位取得と同時に200時間の実習経験が要件となっています。実習室での発達支援の実習授業は、資格取得のために不可欠なものです。これまでに大学院生や研究員が、実習室で実習経験を積み、「臨床発達心理士」の資格を取得し、研究職として、あるいは専門職として発達臨床現場で活躍しています。現在も、多くの大学院生が取得準備を進めています。
研究に目を向けると、双生児を対象にした観察・調査研究が進められています。また、乳幼児の神経科学的研究を進める大学院生も増えてきています。実習室に設置されているNIRS、視線追跡装置、生理計測装置などを用いた実験研究も活発に行われています。また、工学研究グループと共同で、モーションキャプチャーによる運動、社会的相互作用解析もスタートしました。
今後も社会学研究科実習室では、文理融合型の学問の独創性を活かしつつ、大学院生が将来の研究、実践現場で活躍するための教育基盤をさらに充実させていきます。

心理学専攻・実験心理学レポート:
#1:乳幼児はいかにして心理的発達を遂げるのか
社会学研究科 心理学専攻
皆川 泰代 教授
慶應義塾大学大学院社会学研究科の心理学専攻では、実験心理学に重きを置いています。中でも皆川准教授の研究室では、生後5~6か月から2歳くらいまでの乳幼児を対象に、様々な発達検査から子どもの脳の発達過程を乳幼児から研究。対象者を0~2歳に限定するのは、脳はその年代に著しく発達すると考えられ、言葉も発達する時期だからです。またこの時期には、脳の基礎的な部分が出来上がります。
例を挙げると、0歳のある時期に眼帯をしていると、そちら側の目だけ悪くなってしまうのですが、これは非可逆的で、後から修正が効きません。それだけに、乳幼児の発達と心理の関係を解き明かすことが大きな課題といえるのです。
プレイルームでの発達検査

基本的な発達検査はキャンパス内に設置しているプレイルームで行われます。天井に設置されたドーム型のデジタルカメラによって、乳幼児の動きをリアルタイムで隣の部屋にある多方向モニタリングシステムで観察することもできます。
プレイルームで行われる乳幼児の発達検査にはいくつかの方法があります。母親の膝に抱えられた乳幼児の目の前で、赤を中心とした原色系の小物を振り、それをちゃんと目で追うか、あるいは手を出して握ろうとするかなど様々な反応を確認。この検査によって明らかになるのは、運動機能や手先の器用さで、ものの握り方からも発達段階のレベルを確認できます。この実験室には少数ですが、早産や、兄弟に自閉症児がいるリスク児と呼ばれる子どもの来訪もあります。そのような子どもたちに段階的に発達検査を行い、明らかになった言語や社会性の発達と、別途得られた発達初期の脳機能データやアイカメラの指標がどのように関係しているかを検討します。つまり、発達初期での脳反応が後の発達を予期するかを明らかにし、できるだけ早期に発達障害を見極める方法を見つけ出すことが研究の目的です。
防音室での脳機能検査

この7~8年間、乳幼児の脳機能を検査していく中で明らかになってきたのは、赤ちゃんの脳は、大人の脳と多くの共通項があり、発達のレベルは以前から考えられていた以上であること。最近は、前頭葉と言語野などの脳と脳の結びつきを調べることも出来るようになってきました。例えば新生児でさえ、母親の声を聞いた時に自分がよく知っている声だということを同定し、その母親の声が言語野を活性化させるということが分かってきました。新生児の内から母親の声に反応する理由は、お腹の中にいる時から、よく耳にしていたからだと考えられます。逆に、生まれてすぐに母親から引き離され、長い入院生活などのため母親の声を聞いていないと、自分の母親の声には反応しなくなることもあります。これらの新生児の研究は慶應義塾大学医学部小児科学教室との共同研究です。
このような音声に対する脳機能を研究するため、防音室において近赤外分光法(NIRS)を用いた実験を行っています。NIRS計測では乳幼児の頭にセンサーを付けて、脳機能の検査を実施します。脳の一部が活性化すると、血流が盛んになり、その部分に光を照射した際、光がヘモグロビンに吸収され戻ってくる光量が減少します。具体的には、検出プロブと呼ばれるセンサーで、脳のどの箇所が活性化しているかを判断するのです。
他にも、母子愛着と脳の発達関係の研究から自閉症スペクトラム障害の発生原因の解明へも糸口を見つけつつあります。
発達心理学分野との共同研究
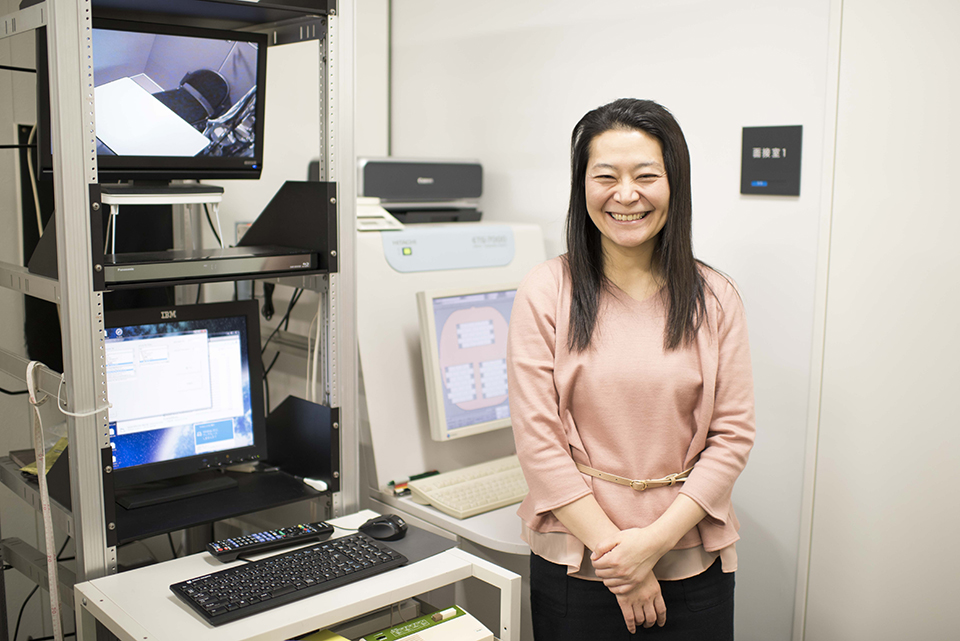
最近は、発達心理学の山本教授と、発達障害の子どもについての共同研究も行っています。自閉症スペクトラム障害の子どもについても、NIRSを使っての検査を実施。例えば、アとエの母音の違いを、1歳過ぎている普通の子どもや大人は、左優位で処理します。一方、自閉症の子どもは、乳幼児の頃と同じように、両方の聴覚野に同じような反応が出ます。兄弟に自閉症児がいるリスク児でも、3歳ぐらいまでは、まだ自閉症スペクトラム障害かどうかの診断は付きません。そのような子どもたちには、0歳、1歳、2歳、3歳と段階的に追跡研究を続けます。
脳機能検査においては、NIRSとアイカメラと、両方を組み合わせて検査することもあります。例えば、目の前で話をしている人がいる場合に、相手の人の目を見ているのか、あるいは口を見ているのか、などということも分かります。一時期は、話をしている大人の口元を見る子が、言語発達が優れていると言われていたのですが、相手の目を見る子の方が、言語発達が優れているとも言われていて、色々な意見があるようです。