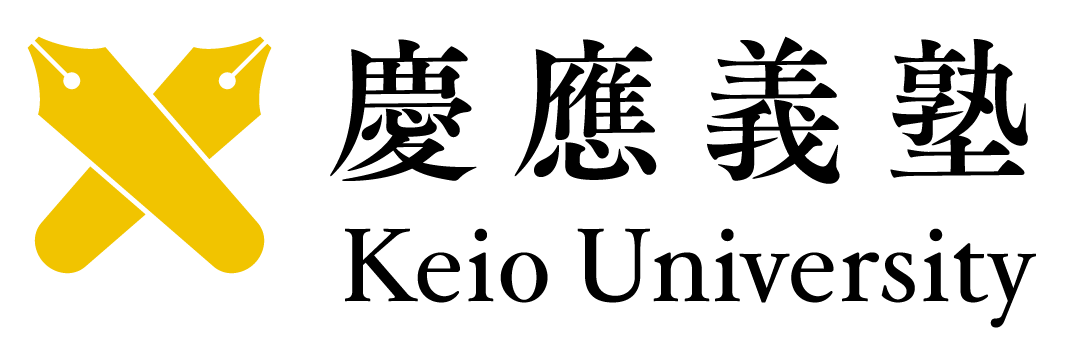学生生活
研究を追求する楽しさ
川原 伶王
社会学研究科 社会学専攻
修士課程1年(2024年度現在)
皆さんは「秋葉原」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。電気街、オタク文化、東京の大都市のひとつ、AKB発祥の地、メイド喫茶 ―こうした多彩な要素が頭に浮かぶのではないでしょうか。
私にとって都市とは、多様で複雑な要素が絡み合う場です。その中で、一つの要素だけが街を形作るのではなく、さまざまな要素が交ざりあっていることこそが街の魅力だと考えています。このような都市の複雑性を深く理解し、考察を深めるためには、自分ひとりでは限界があることを痛感しました。
大学院進学を決める際、私が重視したのは、こうした多様な街の側面についてどこまで広く、そして深く探究できる環境があるかどうかでした。私が所属するゼミは、異なる分野に専門性を持つ方々が集い、それぞれの視点から議論を重ねられる場です。また、外部講師の方々との交流を通じて、多角的な視点や知識を得られる授業が豊富にあることも、本校を選んだ大きな理由の一つです。
慶應義塾大学の社会学研究科での1年間の学びを通じて、毎回の授業や議論から新たな視点を得る喜びを感じています。それが研究の進展にもつながり、日々の学びが楽しく充実したものになっています。
これから入学を考えている皆さんにも、研究を深めることの楽しさや、新たな発見の喜びをぜひ体感していただきたいと思っています。
研究を通して心を探求する
鈴木 菜穂
社会学研究科 心理学専攻
博士課程2年(2024年度現在)
悩みや悲しみを誰かと共有すること、あるいは自問自答のように自らの中で深めていくことは、多くの人にとって自然な営みです。では、そもそも自分の"悩み"や"悲しみ"をそれとして認識できないとしたら、ストレス反応にどのように対処すればいいのでしょうか。私の研究テーマは、このような感情の認識・言語化が困難な性格特性であるアレキシサイミアに着目したものであり、臨床場面への橋渡しとなるような研究知見を得ることを目指しています。
大学入学当初は、本格的に研究活動をしていくことは考えていませんでしたが、ある一つの論文を読んだことが転機となり、次々と関連する研究論文を読み進めていく中で、もっと深く知りたいという探究心に駆られました。この経験が、現在取り組んでいる研究テーマに向かう原動力となっています。博士課程に進学してからは、遠い存在に感じていた研究者たちと実際にディスカッションをする機会にも恵まれ、研究を進める中で自分の世界が一気に広がったことを実感しています。
最初は小さな興味でも、それを深掘りしていくことで学問の世界は驚くほど広がります。研究には困難も生じますが、そこで得られる学びと出会いはかけがえのないものです。皆さまと共に議論できる日が来ることを心待ちにしています。
「トンネル」を進み続ける
本郷 直人
社会学研究科 教育学専攻
修士課程2年(2023年度現在)
私は、日本教育思想史を専門として、明治末期から昭和戦前期にかけての教育思想と哲学者西田幾多郎(1870-1945)の影響関係について研究しています。
私が大学院に進学する決意をした際、内面から湧き出る「問い」に対し、自分なりの「答え」を探し続けることへの強い衝動が存在していたように思えます。大学院では、このような「問い」を絶えず反省する環境を提供してくれます。特に教育学専攻では哲学、心理学、歴史学、比較教育学など多岐にわたる領域が存在し、多様な視点からの議論を通じて、様々な刺激を受けることができます。このような「陶冶」の経験を通じて、「問い」を抱くことの価値を再確認し、「答え」を追求し続けることができる場所、それこそが大学院だと私は考えます。大学院生活は試行錯誤の連続で、まるで暗闇の「トンネル」を進み続けるかのように、進むべき方向も、到着点も見通すことができないなかで「答え」を探し求めます。しかし、大学院での多様な交流を通じて再認識した、内面から湧き出る「問い」の価値を信じることで、私は「トンネル」を一歩ずつ進み続けることができたと思います。大学院に進学した皆様と「問い」をめぐって議論できる機会を楽しみにしております。
探求の日々
新井 真帆
社会学研究科 社会学専攻
博士課程1年(2023年度現在)
私は学部生の頃より、「共生」について関心をもち続けてきました。修士修了後には、民間企業に就職し、外国にルーツをもつ人や障害をもつ人を含んだ様々な人々と働く機会をもちました。その中で、実社会において「共生」を目指すには様々な課題があることを身に染みて感じ、そしてその課題について探求したいと考え、博士課程への進学を決意しました。現在は、博士課程に在学しながら公益財団法人で働いており、研究・実践双方の視点から、「共生のありかた」について探求する日々を過ごしています。将来は、博士課程と社会人、両方の経験を活かし、様々なルーツをもつ人々の橋渡しをする役割を果たすことができればと考えています。
「大学院とはどのような場か?」という質問には、「じっくりと考え、議論ができる場である」と答えます。自身の研究についてじっくりと考え、加えて授業等において他の履修生や先生方と議論を重ね、自分にはなかった視点や考え方を得ることができるのです。「じっくりと考え、議論ができる場」というのは、今日の社会の中では貴重な場なのではないでしょうか。大学院進学を検討されている方にも、ぜひこの場で探求していただきたいと思います。
「身体」と「脳」から「心」の謎を読み解く
櫻木 麻衣
社会学研究科 心理学専攻
修士課程2年(2023年度現在)
私は、認知神経科学研究室で、人間の身体反応と思考状態の遷移との関係性について研究しています。私たち人間の「心」は、(少なくとも起きている間は)常に何かを感じ、考えています。その間も、私たちの「身体」、目や耳、手や足、そして内臓は活動を続けており、これらのはたらきを制御するのが「脳」です。この三者の関係性から、まだ明らかになっていない、人間の認知システムについて解明しようというのが、私の、そして私の所属する研究室の、最大の目標です。
「なぜ大学院に進学したの?」「どうして研究をしているの?」とよく聞かれます。私にとっての「研究」の最大の魅力は、自身が抱くまだどこにも答えのない疑問を、自身の手で解決するチャンスが与えられることです。そして、「大学院」で研究をしていると、知識・経験の豊富な先生方や先輩方、そして、様々な資料や実験機材という、心強すぎる味方とともに、このチャンスを追求することができます。迷ったり、失敗したりすることもありますが、自分の「なんで?」の答えを少しずつ見つけながら、刺激的な日々を送っています。
大学院への進学を考えている方には、どんなに素朴でも、たとえ間違っていてもいいので、自分で何かを考え、発信することをおすすめします。その些細な疑問やアイディアが、新たな研究への第一歩となるでしょう。
自由に「悩める」場
佐藤 雄一郎
社会学研究科 教育学専攻
博士課程3年(2023年度現在)
私の大学院生活の大半は「悩むこと」で過ぎています。例えば、1日中PCの前で呻き、頭を抱え、壁を見つめ、意を決して文章を書き、そうして書き上げた文章を次の日に全て書き直すといった具合です。
こうした「決めかねたり、思いあぐねたり」ということが頻繁にあるのは、正解がない問いに答えようとしているためです。例えば私の場合は、「よい授業を支える教師の専門的力量とはなにか」について考えています。
この「試行錯誤」の過程はあまり楽しいものではありません。しかし、自分が決めたテーマについて、論を吟味し、データや資料を精査し、自分なりの結論を立て、それを適切な言葉や数字で表現するという活動にはよろこびがあります。例えば、山登りの苦労とよろこびに似ているかもしれません。
こういった正解がない問いに数年間にわたって「正対」する上で、資料・情報、指導教授、ともに学ぶ仲間といった環境を提供してくれるのが大学です。特に教育学専攻では多様な領域の専門家(哲学、心理学、歴史学、比較教育学等)が在籍しているため、「そもそもよい授業とはなにか」といった根本的な原理から見直すきっかけをもらえるのが特徴だと思います。
入学を検討されている方には、自由に悩める場であることをお伝えしたいです。自由を認める環境がある一方、その厳しさもあります。ぜひ自身の関心を「追求」してみてください。
私の研究にとっての快適な場
ゼルマー, コナー D.
社会学研究科 社会学専攻
修士課程2年(2022年度現在)
私は慶應義塾大学の評判や設備について何も知らずに入学しました。唯一知っていたのは慶應義塾大学大学院社会学研究科の先生が、私の興味につながる研究をしているということだけで、それだけの理由で私は慶應で研究することを決めたのでした。私の研究関心は日本人女性および彼女たちの妻、母親、労働者としての経験にありました。社会学研究科に入学して、先生が研究を指導してくれるだけでなく、その研究に精通していたことは、私にとって本当に幸運なことでした。私の指導教員の先生は、私が行う研究の方法と目標の基盤となる重要な研究を紹介してくれました。現在私は、日本の母親の実態を明らかにするために、参与観察とインタビューに基づく質的調査を行っています。具体的には、日本の母親と父親がどのように性別の役割を認識し、その役割が彼らの行動にどのような影響を与えているかを調査しています。
日本での留学生活は得てして大変です。言葉、文化、そして物事の進め方が、私の出身国とは信じられないほど違います。しかし、このような困難にもかかわらず、先生は私の日本語を辛抱強く理解し、社会的に不適切な振る舞いを理解し、授業での議論において私の視点を大切にしてくれています。指導教員や他の先生方のサポートがなければ、私の日本での研究はうまくいかなかったでしょう。慶應義塾大学で、私の研究のために協力してくれる人たちに囲まれながら、研究の場を見つけることができたのは幸運だったと思っています。
知識の最前線に立つという楽しみ
鈴木 結子
社会学研究科 心理学専攻
博士課程2年(2022年度現在)
私は動物心理学研究室でカラスの音声コミュニケーションの研究をしています。大学院進学を決めたのは「なんだか面白そう」というふんわりした理由でした。大学院に進学して三年ですが、今思うとその直感は間違ってもいましたが、正しくもあったと感じます。先生の授業を受けることは少なくなりますが、疑問を持って自ら聞きに行けば豊富な経験を語ってもらえます。後輩の相談には責任を持って答えねばなりませんが、先輩は頼れる存在です。研究に休みはありませんが、自分の決断で進めることができます。
大学院へ進学したいと思っている方におすすめしたいのは、冷静に自分のペースを守ることです。大学を卒業してから大学院への進学を決める人は決して多くはありません。ほとんどの大学院生は親戚や友達と少し違った人生を歩むことになると思います。私も学部時代の同期と比較して焦りを感じることもよくありますが、「すぐには結果が出なくても、研究は楽しい!」と思い込める力が役に立っています。
大学院生活で私が最もわくわくするのは、たくさんの知識を集めてもなお、「人類の誰も知らないこと」がその先にあると分かった時です。正しい答えがすでに決まっている問題を解いていた「勉強」を超えて、誰も知らない世界の仕組みを(ほんの少しだけでも)解き明かせるのが、研究の楽しさだと思います。