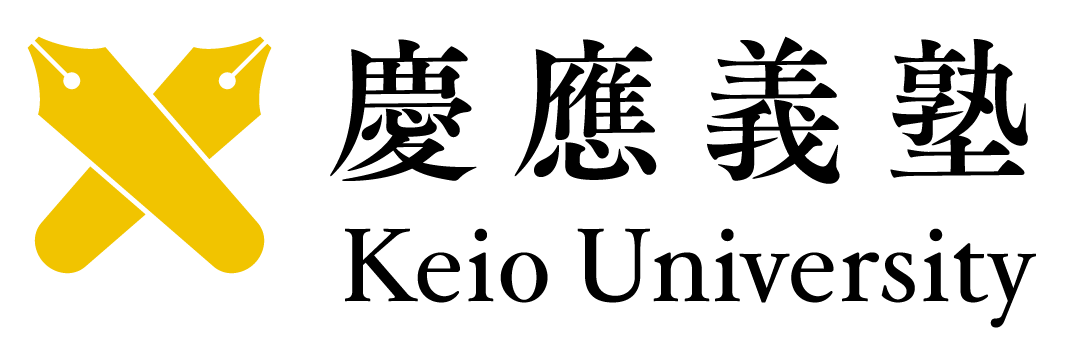研究科委員長メッセージ
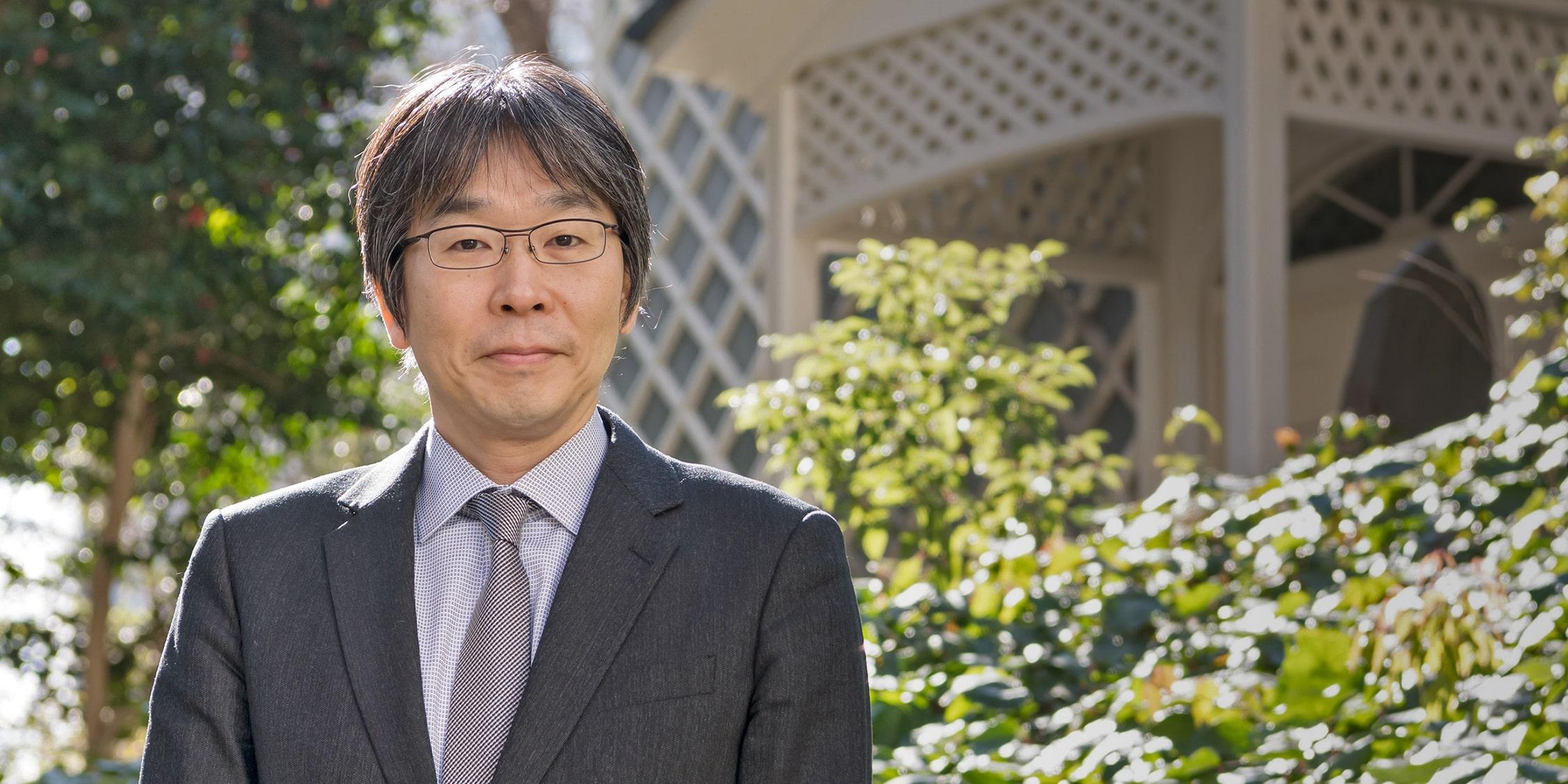
変化を見極め、 限界を突破する! 社会学研究科委員長 梅田聡
我々が今生きている時代は、急速な変化に満ちあふれています。以前は、普及に10年かかったものが、インターネットやSNSの発展により、今は1週間程度で同じレベルに到達されます。このような時代の急速な変化に対し、社会も、人も、それに応じた変化を余儀なくされます。しかし、この変化に追いつけることもあれば、追いつけずに歪みが生じることもあります。フェイクニュースや詐欺といった話題が席巻し、「信じる」という心の機能が時代の流れに追いつけなくなっているのは、その典型的な例といえます。また、SNSやAIの発展のように、急速な変化が見えやすいものもある一方で、生物の進化や地球温暖化のように、緩徐な変化のために気づきにくいものもあります。我々は、こうした変化の時間スケールが異なるさまざまな事象に囲まれて生活しています。そして、生物も社会も、見えやすく、気づきやすい変化に影響を受けるだけではなく、見えにくく、気づきにくい変化の影響も受けています。このような世の中で我々に求められるのは、変化を見極める能力と、それに対応する柔軟な思考力、そして、その問題に立ち向かい、それを突破するスキルです。
大学院で学んでいる皆さん、あるいは大学院に進学しようとしている皆さん、大学院では何を学び、何を身につけることができるのでしょうか。「自分が関心のある領域に関する理解を深める」、「研究に必要とされる調査や実験の手法などを身につける」といった回答が多くを占めるのではないかと想像します。しかし、これらは大学院に入学しなくてもできることではないでしょうか。自らでインターネットを利用し、図書館に通い、公開講座などに出かけることでも、ある程度までは達成できるはずです。大学院で学ぶべきことは、実践的な経験を通して解決すべき研究課題を明確化し、それを解決するための最善の方法を探し当てるスキルを身につけることです。
我々、社会学研究科は、社会学専攻、心理学専攻、教育学専攻から成り立っており、多数の学部や研究所に所属する、幅広い専門分野のエキスパートの先生が揃っています。皆さんが関心を寄せる分野について、豊かな経験やスキルを持つプロフェッショナルから、幅広い知識を身につけることができるはずです。しかし、忘れてはならないのは、研究の主体は皆さん自身であるということです。修士課程の2年、博士課程の3年は、決して長いものではありません。限られた時間を無駄にせず、積極的、自発的に動いてください。修士論文や博士論文の内容は、唯一無二のものでなければなりません。既存の研究と少しだけ違うものでも、この条件は満たすことにはなりますが、もっとオリジナルな発想に基づいたものを目指してください。これまでに既に実施された関連研究をしっかり調べ、まずは解決すべき問題が何なのかを考えてみてください。皆さんの指導教授になる方は、その問題に立ち向かうための指針を提供してくれるはずです。そして、それを解決するための手段について、とことん考えてみてください。そうしたら、自分ができることの限界が見えてくるはずです。おそらく、それが大学院レベルの研究のスタート地点です。
スタート地点に立つことができた皆さんが、次に立ち向かうべきは、その限界の突破です。限界が見えてきたということは、逆の言い方をすると、「本当はこれをやればいい」ということがわかっている状態といえるかもしれません。「現実的に考えてこの検証は不可能」という限界かもしれません。しかし、「本当はこうすればできる」という可能性の道筋が見えている場合も多いはずです。ここで、自らに課してしまっている制約を取り払うことが必要です。それは「自分にはこれはできない」という方法論的な制約かもしれませんし、「面倒くさい」という心理的な制約かもしれません。場合によっては、「研究費が足りない」という経済的な制約かもしれません。制約を取り払うことは、研究の「ブレークスルー」を引き起こす最も重要な要件です。ひとつでもよいので、この制約を取り払う気持ちを持ってください。その気概があれば、研究費を取得するなどの手段で、経済的制約すらも乗り越えられるはずです。そして、是非、限界を突破してください。
こうした一連の活動を支える環境として求められる条件は、「研究を学際的に展開できる環境が整備されていること」と「他分野の人と交流ができること」です。慶應義塾は、他学部との研究連携も非常に盛んであり、他の分野の専門家とのコミュニケーションができる優れた環境を提供しています。また、社会学研究科にも多様な国籍の大学院生が所属しています。国外の大学との間で、学術交流協定やダブルディグリー協定も締結しています。また、教育学専攻の修士課程には、現職教員枠も設定されており、研究と教育現場との連携の機会も設けられています。こうした環境に身を置くことで、是非自らに磨きをかけてください。
「共に学び、共に超える」、そんな仲間との出会いを心待ちにしています。